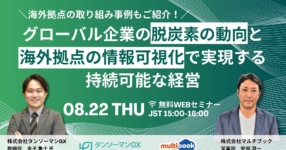近年、カーボンニュートラルへの実現に向けて、多くの日本企業が温室効果ガスの削減に取り組んでいます。
2050年までのカーボンニュートラル実現を達成するために、これから温室効果ガス削減への取り組みを考えている方も多いのではないでしょうか?
「カーボンニュートラルってそもそも何?」
「カーボンニュートラルの先進的な事例が知りたい!」
そこで、本記事ではカーボンニュートラルの意味からSDGsとの関係まで解説します。
効果的に温室効果ガスの削減に取り組み、カーボンニュートラルへの実現のご参考にしてください。
カーボンニュートラルとは

カーボンニュートラルとは、環境省によると「温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させることを意味する」とされています。
つまり、温室効果ガスの排出量が実質的にゼロになっている状態のことを指します。
2020年の菅政権では、カーボンニュートラルを進める方針を宣言しました。
温室効果ガスの排出量を極限まで少なくしたとしても、現段階ではゼロにするのは非常に難しいです。しかし、温室効果ガスを極力出さない方法で事業を行ったり、森林などの自然環境を整えることで温室効果ガスの吸収量を増やすことが必要です。
持続的な社会を作るためには、政府の施策だけでなく、企業の協力が必要不可欠になっています。
カーボンニュートラルとカーボンオフセットの違い
カーボンオフセットとは、温室効果ガスの排出量を実質的にゼロにするという取り組みです。その中では、太陽光や地熱、風力といった再生可能エネルギーの効果的な活用により温室効果ガスを削減することが含まれています。また、大量生産、大量消費といった世界全体の経済基盤の見直しを図ることを目的としています。
やむを得ず、排出された温室効果ガスは、排出量に合わせた削減活動への投資をすることで達成を目指します。
また、カーボンオフセットでは、吸収・削減した温室効果ガスを「クレジット」と言われる市場取引できる商品への交換が可能です。
クレジットを購入することで、温室効果ガスのオフセット(排出量を差し引くこと)できます。クレジットの購入で得た資金は、再生可能エネルギーへ活用や緑化活動の推進などの活動へと循環できます。
こうして、地球温暖化対策が実現します。
一方で、カーボンオフセットは、温室効果ガスの排出量を抑制するものの、オフセットしている活動が必ずしも温室効果ガスの削減に貢献するとは限りません。
こういった、カーボンオフセットの欠点を補うのがカーボンニュートラルの実現です。
カーボンニュートラルでは、自社が排出した温室効果ガス分は削減しなければいけないので、温室効果ガスの排出量が実質的にゼロになります。
カーボンニュートラルの考え方に基づき、温室効果ガスの削減を目指していくことで本当の意味での地球温暖化対策が実行できます。
そもそも温室効果ガスとは
カーボンニュートラルを目指す中で、必要不可欠な知識である温室効果ガスについて解説します。
そもそも、温室効果ガスとは、空気中に含まれる二酸化炭素や一酸化二窒素、メタンガスやフロンガスの総称を指します。
温室効果ガスは、太陽光で温められた熱である赤外線を吸収・放出する性質を持っています。
そのため、地表があたたまる「温室効果」が働いてしまうのです。
この温室効果は、地球の気温を一定に保つ働きがあるため、温室効果ガスがゼロになってしまうと、地球の温度は氷点下19度まで落ちてしまいます。
近年では、温室効果ガスが多くなり、地表がさらに温められているため地球温暖化が進行しの要因になってしまっているのです。
カーボンニュートラルが目指す脱炭素社会とは
カーボンニュートラルを目指すなかで、脱炭素社会や低炭素社会が重要になってきます。
それぞれには、炭素という言葉が入っている通り、英語で炭素という意味である「カーボン」に関連しています。
そもそも、脱炭素社会とは温室効果ガスの大半を占めている二酸化炭素の排出量のゼロを実現する社会のことです。
カーボンニュートラルが、温室効果ガス全体の排出量をゼロにするのを目標にしているため、脱炭素社会を目指すことはカーボンニュートラルに近づくことにもなります。
国際会議の議題に環境問題が上がったのは1970年ごろで、その後京都議定書やパリ協定などで「脱炭素社会」を目指すことが名言されました。
カーボンニュートラルを目指す背景
近年では、地球温暖化の影響が世界各地で出ており、カーボンニュートラルの実現が急務になっています。
例えば、世界各地で起こる異常気象や海水面の上昇による水没のリスク、海水温の上昇による漁獲量の激減など私たちの生活に直結して問題が発生しています。
地球温暖化の原因の1つとされている、温室効果ガスの排出量を実質的にゼロにするカーボンニュートラルが有効な対策とされています。先述のとおり、カーボンニュートラルを目指すに至った経緯には、2つの国際会議が関係しています。
京都議定書の作成
まず、1995年に開催された国連気候変動枠組条約締約会議が開催されました。
その後、地球温暖化に対して具体的な取り組み目標である『京都議定書』が作成されました。
そこでは、先進国における温室効果ガスの排出量を1990年時点の5%以上削減することを目標としました。
2008年から2012年の第一約束期間では、先進国加盟国の23ヶ国中約半数の11ヶ国が目標を達成。
この段階では、温室効果ガスの排出量の削減は先進国に留まっていたため、二酸化炭素の排出が多い発展途上国での義務化が求められる声が相次いだのです。
先進国側の不公平感が拭えず、先進国と途上国での意見が対立し、混乱が続きました。
ついに、各国で数値目標を決め、世界全体で温室効果ガスの削減に取り組む動きは、パリ協定へと持ち越しになってしまいました。
パリ協定の締結
京都議定書に代わり、2015年には2020年以降の取り組みを決定した『パリ協定』が締結されました。
パリ協定では、「世界全体の平均気温上昇を産業革命時代に比べて2℃以下に保ち、かつ1.5℃に抑える努力」が世界目標として掲げられました。
加えて、温室効果ガスの排出量や吸収量の均衡をとるために、最新の技術を使って早期の温室効果ガスの削減を目指すと決定。
京都議定書では、先進国だけの目標でしたが、パリ協定では、発展途上国にもカーボンニュートラルへの取り組みが不可欠です。
カーボンニュートラルに対する日本政府の動き
本章では、カーボンニュートラル実現のために日本政府が行っている動きについてご紹介します。
『地球温暖化対策推進法』の改正
これまで、問題となっていた地球温暖化を抑制するために成立した『地球温暖化対策推進法』が以下の点が改正されました。
- 2050年までのカーボンニュートラルの実現を基本理念とすることを明記
- 地方創生に繋がる再生可能エネルギーの導入および利用促進
- ESG投資に繋がるように、企業が温室効果ガスの排出量の情報をオープンデータとして公開
今後も、随時改正していきカーボンニュートラルの実現へ向けて日々進んでいます。
地域脱炭素ロードマップの策定
環境省は地域脱炭素ロードマップを策定し、カーボンニュートラルの実現に向けて2030年までに集中して行う、地域での脱炭素に対する具体的な取り組みを示しました。
そこでは、人材や情報、技術や資金などの積極的な支援を行うとしています。
また、地域脱炭素ロードマップでは、次の2点を中心として目標を掲げ、推進する予定です。
- 2030年までに、最低でも100箇所以上の脱炭素先行地域を作る
- 日本全国で、太陽光発電や省エネ住宅整備、電気自動車の推進
これらを後押しするための基盤となる施策も同時に行うことで、脱炭素先行地域の広がりを目標にしています。
2050年以前に、カーボンニュートラルの実現を目指しています。
グリーン成長戦略の策定
グリーン成長戦略では、経済と環境の好循環を作ることでカーボンニュートラルを目指す産業政策です。
カーボンニュートラルは、既存のエネルギーの変換や莫大な設備投資などかなりの努力が必要になります。
そのため、政府では今後成長が期待される次の14分野への重点的な推進を実施するとしています。
| エネルギー関連産業 | 輸送・製造関連産業 | 家庭・オフィス関連産業 |
| 洋上風力・太陽光・地熱 水素・燃料アンモニア 次世代熱エネルギー 原子力 | 自動車・蓄電池 半導体・情報通信 船舶 物流・人流・土木インフラ 食料・農林水産業 航空機 カーボンリサイクル・マテリアル | 住宅・建築物・次世代電力マネジメント 資源循環関連 ライフスタイル関連 |
カーボンニュートラル実現に向けた日本企業の事例
特に難しいとされている製造業を中心に温室効果ガスの削減の取り組みについて日本企業の事例をみていきましょう。
トヨタ自動車株式会社
日本の最大大手自動車メーカーである、トヨタ自動車株式会社は、2015年に二酸化炭素の排出量に関する『トヨタ環境チャレンジ2050』を発表した。
ここでは2050年に新車の二酸化炭素排出量を2010年比で90%削減。循環型社会やシステムの構築、グローバルこうじょうの二酸化炭素排出量ゼロなど、6つの取り組みにチャレンジすることを宣言しました。
当初2050年までとしていた、二酸化炭素排出量のゼロ目標を2035年に前倒しすると2021年に発表しました。
さらに、2030年までに世界で年間350万台もの電気自動車の販売を目指すなど、カーボンニュートラルを加速させる動きが続いています。
ヤマト運輸株式会社
物流業界のトップであり、宅配便のシェアトップを誇るヤマト運輸では、2050年までのカーボンニュートラル実現を目指しています。中期目標として。2030年までに温室効果ガスの2020年比48%削減を目標に掲げています。
具体的には、電気自動車2万台の導入や太陽光発電設備約800件の導入などに取り組んでいます。
また、再生可能エネルギーである、太陽光発電により電気自動車の電力供給にも取り組んでいます。
三菱重工菱重工エンジニアリング株式会社
三菱重工菱重工エンジニアリング株式会社は、カーボンニュートラルの実現に向けて「脱炭素事業推進室」の新設を行いました。
また、関西電力との共同開発による技術開発や独自の二酸化炭素回収技術の導入など様々な取り組みをしています。
特に、アンモニアや水素などの脱炭素技術を利用した技術開発や回収した二酸化炭素を化学品へと転換するなど今後の取り組みに注目です。
日本製鉄株式会社
鉄鋼分野は、脱炭素しにくい分野であるにもかかわらず、日本製鉄株式会社は2050年にカーボンニュートラルを実現を目指しています。その取り組みの一つとして、2021年には
中長期的な経営計画として『日本製鉄カーボンニュートラルビジョン2050』を発表しました。
同社は、二酸化炭素排出量削減のための高機能鋼材とソリューションの提供、鉄鋼製造において脱炭素化しカーボンニュートラルの実現を掲げています。
また、水素を使った還元方法での高級鉄鋼製造を目指すなど新しい技術開発が目覚ましいです。
企業が取り組みやすいカーボンニュートラルへの対応
カーボンニュートラルを目指すには、まず行うべき取り組みがあります。何から始めていいかわからない事業者の方も多いと思うので、以下の取り組みを紹介します。
現在の温室効果ガス排出量の算出と削減目標の作成
カーボンニュートラルを目指すためには、現在の温室効果ガスの排出量を算出する必要があります。温室効果ガスが、数字として見えることで削減目標を作成しやすくなります。
製造業を例にとると、センサーを導入して商品の製造にかかるエネルギーの使用量の把握などが必要です。
実際に自社が排出している温室効果ガスがわかったところで、具体的な削減目標を作成しましょう。
期限は2030年までなど、政府の取り組みに合わせて中長期的な目標がより良いです。
また、自社独自の温室効果ガス削減ロードマップを策定し車内で共有することで、会社全体でカーボンニュートラルへの実現へと近づくことができます。
持続可能な再生可能エネルギーへの転換
風力や太陽光、バイオマスなどの再生可能エネルギーを利用した、資源が枯渇せず。循環的に使えるように切り替えが必要です。
これまでの日本の電力を支えていたのは、火力発電は石炭を燃やし発電するため、燃料の枯渇が懸念されており、発電時に二酸化炭素が発生してしまいます。これにより、温室効果ガスが増える可能性があります。
再生エネルギーへの転換により、循環的にエネルギーが使えるため持続可能な社会へと近づいていきます。
業務効率化による生産性アップ
エネルギーの転換や温室効果ガスの削減などに必要なのは、それだけではありません。
主に、製造業などでは、機械やシステムの自動化による業務効率化を目指すことで温室効果ガス削減をするために他の作業の手間が省け、生産性がアップします。
従来であれば、人が行っていた作業を機械化したり、ビックデータを使ったAIによる効果的なマーケティング施策などを活用することでこれまでより効率的に取り組めます。
また、無駄なコストカットができ、より長時間製造できるなどが期待できます。
温室効果ガスの削減に関する業務に集中して取り組めるため、これまで以上にカーボンニュートラルへと近づくことができます。
カーボンニュートラルとSDGs
カーボンニュートラルとSDGsの達成は非常に密接な関係にあります。
本章では、その関係性やSDGsの目標期限について解説します。
カーボンニュートラルと SDGsの到達目標
カーボンニュートラルと直接関係しているのがSDGsの17のゴールのうち、以下の2つです。
- 目標07「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」
- 目標13「気候変動に具体的な対策を」
もちろん、SDGsも取り組む目標として大切な指標の一つであり、地球温暖化の対策もSDGsへの達成に貢献すると言えます。
また、温室効果ガスが原因とされる地球温暖化の影響による、気候変動や自然災害は、農林水産業に甚大な被害を及ぼしています。
そういった意味では、農作物が取れないことによる目標02の「飢餓をゼロに」や第一次産業での収入がなくなるという意味で、目標01の「貧困をなくそう」にも関係してきます。
さらに、カーボンニュートラルを進める上では、温室効果ガスの排出量の抑制や吸収量の増加には、技術的な課題があります。先進国だけでなく、途上国でカーボンニュートラルの実現のために目標09「産業と技術革新の基盤をつくろう」にも繋がります。
こういった環境問題を解決していくためにはインフラ整備が欠かせません。
先進国は、自国での技術開発のみならず、途上国への技術提供や共同開発が必要になってきます。
カーボンニュートラルを目指す上で課題となっている事柄を解決していくことが、SDGsnのゴール達成へと近づくことにもなります。
SDGsのゴール達成期限
SDGsは2030年までの17のゴール、169のターゲットの達成を目標に掲げています。
この2030年は、カーボンニュートラルを目指す温室効果ガスの削減目標の中間目標でもあります。
日本においては、2030年までに2013年比の46%を削減することを目標にしています。
目標達成のためには、再生可能エネルギーの導入やエネルギー供給の効率化などの政策が中心になっています。
また、政府は2030年までに再生可能エネルギーでの発電量を全ての発電量の22%〜24%程度まで引き上げることを目標に掲げました。
カーボンニュートラル実現に向けてできることから取り組もう
製造業では、商品製造の過程で二酸化炭素が排出されやすいですが、効果的なエネルギーの導入により、カーボンニュートラルの実現が十分可能です。
設備投資や、新技術の開発など莫大なコストがかかると思われがちですが、その一歩踏み出すことで環境問題への解決に貢献できます。
これからも、私たちが生活していくための持続的な社会を作っていくために、この記事が参考になれば幸いです。
著者のプロフィール

- タンソーマンプロジェクト発起人であり、タンソチェック開発を行うmedidas株式会社の代表。タンソーマンメディアでは、総編集長を務め、記事も執筆を行う。