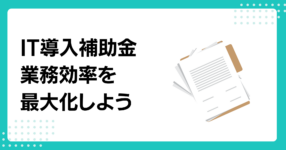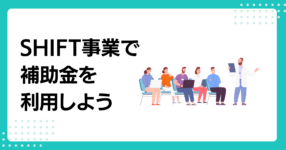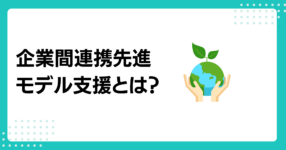ESG投資が金融市場において存在感を増していますが、私たちが暮らす地域社会への影響を正しく理解している人は、多くないのではないでしょうか。本記事を読めば、ESG投資の背景から、地域社会に与える影響と重要性が分かります。
そもそもESG投資とは
ESG投資とは投資機関が投資を行う際、これまで主流であった財務状況だけでなく、非財務情報であるESGの3要素(環境、社会、ガバナンス)への取り組みを考慮する投資手法のことです。ESGは、環境を意味するEnvironmentと社会を意味するSocial、企業の管理体制を意味するGovernanceの頭文字を合わせた言葉です。
近年、世界中の投資機関がESG投資に注力することを公言しており、世界の金融市場におけるESG投資額は、2016年末時点で22.8兆ドルだったものが、2022年末には30.3兆ドルにまで拡大しています。
参照:ESG投資の近年の進展 |ニッセイ基礎研究所 (nli-research.co.jp)
その為、最近では国内の上場企業などの大企業を中心に、ESGへの取り組みに関して積極的な情報開示が行われるようになっています。また、自社のESGへの取り組みに対して投資機関からの評価を受けやすいよう、第三者機関である外部評価会社によりESGスコアを付与してもらう企業も多く見られます。ESGスコアは、ESGへの取り組みを外部評価会社が評価し数値化した指標で、ESG投資における重要な評価指標として活用されています。
参照:投資家の新たな指標「ESGスコア」とは|ビジネスコラム | NTTファシリティーズ (ntt-f.co.jp)
ESG投資で用いられる7つの投資手法
ESG投資と一言でいっても、その投資手法は投資先の評価方法により様々です。ESG投資において主に用いられている投資手法は以下の7つが挙げられます。
1. ネガティブ・スクリーニング(Negative/exclusionary screening)
ESG投資手法の中で、最も古い歴史を持つ手法であり世界中で広く普及しています。武器やギャンブル、たばこ、アルコール、原子力発電、ポルノなど非倫理的であると定義される特定の事業から収益をあげる企業を投資先から外す戦略です。
2. ポジティブ・スクリーニング(Positive/best-in-class screening)
同じ業界、あるいは一定の投資対象の中でESGスコアが相対的に高い企業に投資する戦略です。ESGスコアの高い企業は中長期的な視点で見た際のリスクが低いという発想に基づく手法です。
3. 国際規範に基づくスクリーニング(Norms-based screening)
ESGの国際基準に照らし合わせ、その基準をクリアしていない企業を投資先から外す手法です。代表的な国際基準には、国際連合の「国連グローバル・コンパクトの10原則」があります。これらの原則に基づき、人権問題や環境問題、汚職などの不祥事を起こした企業を外すことで国際社会のルールに則したポートフォリオを構築します。
4. ESG統合(ESG integration)
最も広く普及しつつある手法で、投資先を選定する過程で、従来考慮してきた財務情報だけでなく非財務情報を総合的に分析する戦略です。特に年金基金など長期投資性向の強い資金を運用するファンドなどが活用する傾向にあります。将来の事業リスクや競争力などを図る上で積極的に非財務情報(ESGスコア)を活用し、長期的利益を目指すために用いられます。
5. サステナブル・テーマ投資(Sustainability-themed investing)
持続可能性(サステナビリティ)をテーマとする事業を行っている企業に投資する手法です。再生可能エネルギー、持続可能な農業、男女同権、多様性など、サステナビリティに貢献するテーマに対する取り組みが評価されます。
6. インパクト投資(Impact/community investing)
社会や環境に貢献する技術やサービスを提供する企業を投資対象とし、投資収益に加えて社会や環境に測定可能なポジティブなインパクトを与えることを目的とする投資手法です。ベンチャー企業などに対して行われることが多く、投資機関は直接企業に投資するのではなく、ベンチャーキャピタルを通したESG投資が一般的です。
7. エンゲージメント・議決権行使(Corporate engagement and shareholder action)
株主として企業に対してESGに関する案件に積極的に働きかける投資手法です。株主総会での議決権行使、日常的な経営者へのエンゲージメント、情報開示要求などを通じて投資先企業に対してESGへの配慮を促します。
参照:ESG | 野村アセットマネジメントのESG運用戦略 | 野村アセットマネジメント (nomura-am.co.jp)
ESG投資の地域社会への影響と重要性
ESG投資は投資機関と企業の間だけで完結するものではなく、その影響は地域社会にも及びます。企業のESGへの取り組みにおいて、とりわけE(環境)と S(社会性)は、地域社会との共生や関係性強化を目指すものが多く、これらに注力する企業が増えることで、地域社会の活性化に繋がる事が期待されます。
また、現在企業だけでなく自治体の多くも参画しているSDGsとの関係性を理解することも重要になります。最終的には地域社会そのものも、ESG投資の対象になりうることも忘れてはいけません。
関連記事:ESG投資とは?種類や仕組み、メリット・課題まで解説
SDGsとの関係
SDGsは2015年に国連サミットで採択された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す為の国際目標で、17の目標と169のターゲットから構成されています。SDGsの特徴は、国や自治体、企業、個人まで全てが協力して、地球上の「誰一人取り残さない(Leave no one behind)」ことを誓っている点にあります。
近年では地域社会の持続的な発展の為に、SDGsを政策目標に盛り込む自治体も増えています。SDGsの17の目標には、環境課題や社会課題の解決といった、ESGの取り組みと相関があるものが多く、その為ESGはSDGsで掲げる目標達成の手段と言うこともできます。地域社会の持続的な発展は、ESGへの取り組みがカギを握っているということなのです。
参照:ESGとは? SDGsとの関係とESG投資や経営、取り組み事例まで紹介|SDGsにまつわる重要キーワード解説|講談社SDGs by C-station (kodansha.co.jp)
ESG投資を地方創生の起爆剤とする
このような地域社会でのSDGs達成にむけたESGへの取り組みは、それ自体がESG投資の対象となります。地方にESG投資によって資金を引き込むことができれば、地域社会の継続的な発展に大きく貢献します。
実際にSDGsや地域課題の解決に取り組む中小企業や地方公共団体に対して、金融支援を行う地域の金融機関や大手銀行、証券会社が増えています。長野県では、地域金融機関である八十二銀行と連携して、SDGsに積極的な企業に対し発行手数料を割り引く「地方創生・SDGs応援私募債」という金融商品を提供しています。ESG投資が今後地方創生の起爆剤となることが大いに期待されます。
参照:地方創生にESG投資引き込め | 日経ESG (nikkeibp.co.jp)
ESG投資の盛り上がりと企業側の成功事例
ESG投資が注目を集めるきっかけとなった出来事のひとつに、2006年に当時の国際連合事務総長であるコフィー・アナン氏が金融業界に対して提唱したPRI(Principles for Responsible Investment:責任投資原則)があります。このPRIの中で、投資機関の意思決定プロセスにESG課題を反映させることが、投資のリスクマネジメント及び社会的責任になることが提言されました。
提唱後すぐの2008年にリーマン・ショックが起きた事により、投資家の関心が短期的な経営指標から長期的な経営指標に変化したことで、PRIが注目を浴びESG投資への関心が拡がっていきました。
PRI(責任投資原則)
PRI(責任投資原則)は法的拘束力のない任意原則であり、投資機関が責任ある投資を推進するための行動指針や原則が書かれた、ガイドライン的な性格を持つ国際的なイニシアティブです。投資機関が投資を行うにあたってESG課題を反映させるべきとし、6の原則と35の具体的な行動が示されています(下記表参照)。PRIに署名した参画機関は2022年末現在で5,314機関にのぼり、運用資産合計は121.3兆ドル(1ドル=135円換算で約1京6000兆円)にもなり、日本のGDPの約30倍もの規模を誇ります。
| 6の原則 | 35の具体的な行動 |
| 私たちは、投資分析と意思決定のプロセスにESGの課題を組み込みます | 投資方針ステートメントでESG課題を取り入れる |
| ESG関連ツール、測定基準、分析の開発を支援する | |
| 内部の投資マネージャーのESG課題組み込み能力を評価する | |
| 外部の投資マネージャーのESG課題組み込み能力を評価する | |
| 投資サービス・プロバイダー(金融アナリスト、コン サルタント、ブローカー、調査会社、格付け会社等)に対し、進化する調査・分析にESG要因を組み込む ように依頼する | |
| このテーマに関する学術研究等を促す | |
| 投資専門家を対象としたESG研修を提唱する | |
| 私たちは、活動的な所有者となり所有方針と所有習慣にESGの課題を組み入れます | 本方針に沿ったアクティブ・オーナーシップ方針を策定・開示する |
| 議決権を行使し、(外部委託の場合は)議決権行使方針の遵守をモニターする | |
| エンゲージメント能力を(直接または外部委託により)開発する | |
| 方針、規制の策定、標準設定(株主の権利の促進・保護等)に参加する | |
| 長期的なESGの考慮に沿った株主決議を提出する | |
| ESG課題に関し、企業にエンゲージメントを行う | |
| 協働エンゲージメント・イニシアティブに参加する | |
| 投資マネージャーに対し、ESG関連エンゲージメントに取り組み、その報告を行うように依頼する | |
| 私たちは、投資対象の主体に対してESGの課題について適切な開示を求めます | (Global Reporting Initiative などのツールによ り)ESG課題に関して標準化された報告を求める |
| 年次会計報告書にESG課題を組み込むように求める | |
| 関連する基準、標準、行動規範または国際イニシアティブ(国連グローバル・コンパクトなど)の採用または遵守に関する情報を企業に求める | |
| ESGの開示を促進する株主のイニシアティブや決議を支援する | |
| 私たちは、資産運用業界において本原則が受け入れられ実行に移されるように働きかけを行います | 提案依頼書(RFP)に本原則に関連する要件を含める |
| 投資マンデート、モニタリング手順、パフォーマンス指標、インセンティブ体制を適宜調整する(例えば、該当する場合、投資管理プロセスが長期間を反映するようにする) | |
| ESGの期待事項を投資サービス・プロバイダーに伝える | |
| ESG期待事項を満たしていないサービス・プロバイ ダーとの関係を見直す | |
| ESG統合のベンチマーキング・ツールの開発を支援する | |
| 本原則の実施を可能にする規制または政策の開発を支援する | |
| 私たちは、本原則を実行する際の効果を高めるために協働します | ネットワークやツール、ガイダンス資料、投資家のリポーティングなどを学習のリソースとして活 用できる共有の情報プラットフォームへの参画あるいはサポートをする |
| 新たに発生する課題に対して協働して対処する | |
| 適切な協働イニシアティブを展開し、または支援する | |
| 私たちは、本原則の実行に関する活動状況や進捗状況に関して報告します | 投資慣行内でESG課題がどのように統合され ているかを開示する |
| アクティブ・オーナーシップ活動(議決権行使、エンゲージメント、方針対話)を開示する | |
| 本原則に関し、サービス・プロバイダーが必要としているものを開示する | |
| ESG課題および本原則について受益者とコミュニケーションを取る | |
| コンプライ・オア・エクスプレイン(遵守を求め、 不遵守の場合はその理由の説明を求める)アプローチにより、本原則に関する進捗・達成を報告する | |
| 本原則の影響の見極めに努める | |
| より広範なステークホルダー集団の中での認識を高めるため、報告を利用する |
参照:PRI(責任投資原則)とは? 実践的な取り組み事例を交えて解説:【SDGs ACTION!】朝日新聞デジタル (asahi.com)
日本国内でのESG投資の盛り上がり
欧米に比べてESG投資への盛り上がりにかけていた日本ですが、国内でESG投資の注目度が一気にあがるきっかけとなったのが、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)のPRIへの署名とESG投資への参加でした。GRIFは、厚生年金保険や国民年金の財源となる年金積立金を国民から預かり、管理・運用を行っている組織で、その運用資産額は159兆円と世界最大級の年金基金です。また同時に国内外の債券や株式に幅広く投資を行う「ユニバーサル・オーナー」でもあります。
このGPIFが2015年にPRIに署名し、2018年にESGスコアに連動する運用資産額を3.5兆円に増やしました。それにより、国内企業がESGを意識した情報開示や評価機関への対応を活発化させ、近年の国内におけるESG投資の盛り上がりに繋がっています。
参照:機関投資家のESG投資 | 日本取引所グループ (jpx.co.jp)
ESG投資を呼び込みたい企業側の成功事例
企業としては、ESG投資の投資先となれば事業の安定や拡大に繋げることが出来るため、ESG投資の盛り上がりはビジネスチャンスでもあります。国内にはESGへの取り組みを強化させ、高いESGスコアを得ることに成功した企業が出てきています。
花王株式会社
化粧品大手の花王は、2019年に自社のESG戦略である「Kirei Lifestyle Plan」を発表し、ESGを根幹に据えた経営に大きく舵を切ることを宣言しました。2040年カーボンゼロ、2050年カーボンネガティブ実現を掲げ、PET容器への再生プラスチック使用率を2025年度までに100%に、製品廃棄物の削減率を2030年度までに2020年度対比95%削減、ユニバーサルデザインガイドラインに適合する新製品の比率を2030年度までに100%するなど、高い目標を掲げてESGに取り組んでいます。
それにより、花王のESGスコアは世界的なESGスコア評価機関において軒並み高い評価をえており、投資機関から高い信頼度を誇るMSCI格付けでは最上のAAAに次ぐAAのスコアが付与されています。
イオン株式会社
小売り大手のイオンは、ESG経営の根幹として「イオンサステナビリティ基本方針」を掲げ、「環境」と「社会」の両側面で地域に根ざした活動を積極的に推進しています。環境面では「イオン脱炭素ビジョン2050」を発表し、2040年までに店舗で排出するCO2ゼロを目指し、店舗でのエネルギー使用量削減による省エネや再生エネルギーへの転換に取り組んでいます。また2020年3月からは、全モールにおいてプラスチック製ストローの提供を廃止しています。社会面では、イオン幸せの黄色いレシートキャンペーンを展開し、レジ精算時に顧客が受け取った黄色いシートを地域のボランティア団体名が書かれたBOXに投稿すると、レシート金額の1%をイオンが団体に寄付する活動を行っています。
これらの取り組みが評価され、イオンのESGスコアは多くの評価機関から高い評価をえており、MSCI格付けではAAのスコアが付与されています。
参照:イオン サステナビリティ基本方針 | イオンのサステナビリティ | イオン株式会社 (aeon.info)
ESG投資はこれからどうなるのか?
世界の金融市場におけるESG投資額は、2015年末時点の662億ドルから2021年末には9,281億ドルと、6年間で14倍に拡大しました。また日本国内の機関投資家の運用総額に占めるESG投資の割合も、2016年には20%以下だったのが、2021年には60%を超えています。
参照:kyosai20221125-3-2.pdf (mof.go.jp)
ESG投資の拡大の一方で、反ESG投資の動きも一部では出てきています。ESG投資の主導国であるアメリカのフロリダ州では、23年5月にESG投資の活動を制限する「反ESG法」が成立し、他の一部の州でも同様の動きが見られます。
反ESG投資の要因には、ESG投資により石油や石炭関連産業への投資が縮小し、世界的なエネルギー価格の高騰を引き起こしている点や。ESG投資を進めた投資機関が十分な利益を得られていない点が挙げられます。しかし、これら反ESG投資の動きは、ESG投資への揺り戻しと捉える指摘が多く、現に世界的なESG投資拡大の流れを止めるまでには至っていません。
参照:反ESG | 日経ESG (nikkeibp.co.jp)
ESG投資を円滑化する為のルールが整備されていく
ESG投資において、ESGスコアは投資先を選定するにあたって最も重要な指標となります。このESGスコアの評価手法にバラツキがあることが課題として指摘されています。これは、各スコア評価機関が異なる価値観や評価基準に基づいて評価を行っていることや、評価の根本となるESG関連の情報開示に、企業側の制約があることが要因となっています。
このような課題を受け、ISSB(International Sustainability Standards Board、国際サステナビリティ基準審議会)が最初の国際的なESG開示体系として「IFRSサステナビリティ開示基準」を制定し、企業の情報開示方法のガイドラインを整備しています。ESG投資を円滑に行うための仕組み作りが世界的に進んで行くことで、今後さらにESG投資へ投資マネーが流れていくことが予想されます。
参照:GPIFの「ESG活動報告」から見るESG投資の課題 | SOMPOリスクマネジメント (sompo-rc.co.jp)
まとめ
ここまで、ESG投資が広がった背景から、地域社会に与える影響まで紹介してきました。
ESG投資額はここ数年で数倍に拡大しており、私たちが暮らす地域社会に大きな影響を与えています。今後企業や自治体がESG投資の恩恵を受けることができるかどうかが、地域活性化のカギになっていくことが予想されます。