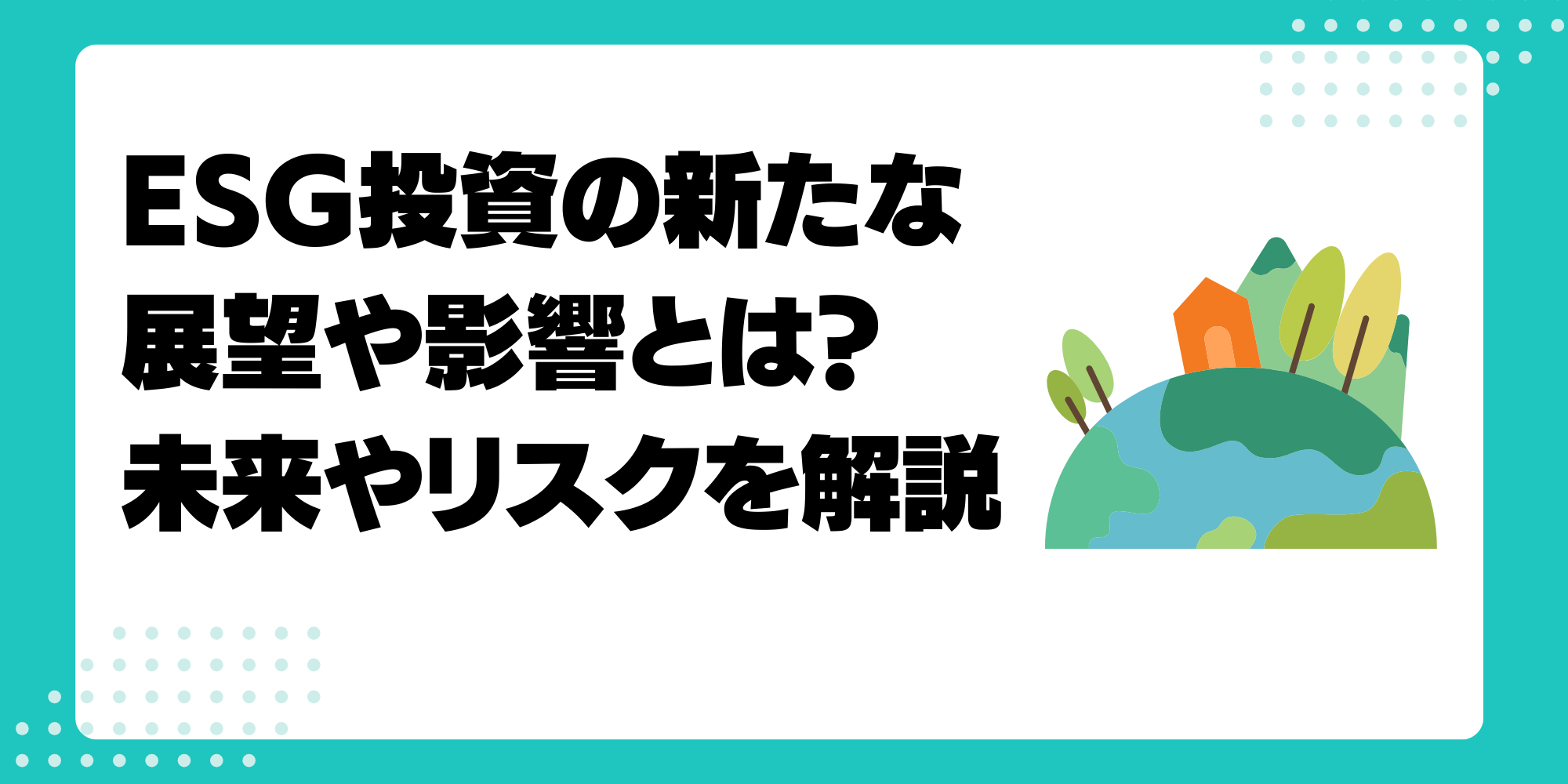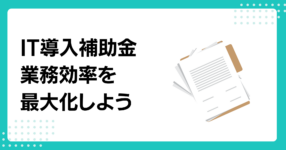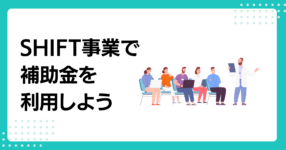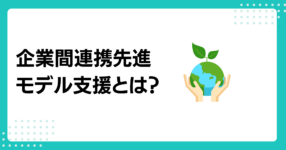近年、ESG投資という言葉を耳にする機会が増えました。しかしESG投資の実態を知らない人は多いのではないでしょうか。本記事を読めば、ESG投資の動向や今後の展望について理解することが可能になります。
ESG投資が企業に与える影響
ESGとは環境を意味するEnvironmentと社会を意味するSocial、企業の管理体制を意味するGovernanceの頭文字を合わせた言葉です。 ESG投資とは、投資家が企業に投資する際、財務状況だけでなく非財務情報である、ESGの3要素(環境、社会、ガバナンス)への取り組みを考慮する投資手法のことです。
近年、企業が経営を行う上で配慮すべき事項として、ESGの要素が重要であるという考え方が投資家や一般消費者にも拡がっています。ESGの取り組みが不十分な企業は、長期的に成長が見込めない企業であると評価を受ける傾向があります。企業がESGを無視した事業活動を行うことは、経営に大きなリスクを与える可能性があると言うことです。
国内の上場企業などの大企業を中心に、ESG分野に関する積極的な情報開示が行われるようになっています。今後投資家がESG情報を重視して、投資先を評価するようになれば、ESGに関する取り組みや情報開示の質が企業価値に大きな影響を与えていくことが予想されます。
ESG投資は金融市場にどう影響するのか?
ESG投資額は、金融市場に占める割合をここ数年で急速に拡大しています。2015年末時点で662億ドルであった世界全体の投資額は、2021年末には9,281億ドルにまで拡大しています。
参照:世界と日本のESG投資動向GX推進を契機にESG投資の拡大へ | 三菱総合研究所(MRI)
これまで投資先を選定する際、企業の業績や財務状況を評価基準として企業価値を判断するのが一般的でした。そのためESG投資先として、優良な企業を判断する評価方法の確立が金融市場における課題となっています。
現在ESG投資において、投資先の評価に用いられる指標はESGスコアが一般的です。ESGスコアは第三者機関である外部評価会社により集計、分析された、ESG分野への取り組みがスコア化されたものです。しかし企業の財務情報とは異なり、ESG分野への取り組みは、非定量的な事項も多く数値化しにくい特性があります。
ESGスコアは、スコアリングの要素を総合的に考慮して実施する「総合型」と特定のテーマについて実施する「テーマ型」に分かれています。 総合型は、ESGの全ての要素について総合的に評価をする一方で、テーマ型はCO2排出量など特定のテーマについて評価するため、企業の特徴的な取り組みを詳しく知ることができます。
大企業の多くは、複数の外部評価会社を利用して、自社のESGスコアを算出・開示しており、投資家は開示情報を元に企業のESGへの取り組みを評価し、投資を行います。
参照:投資家の新たな指標「ESGスコア」とは|ビジネスコラム | NTTファシリティーズ (ntt-f.co.jp)
ESGスコア評価機関の影響力
ESG投資において重要な指標となるESGスコアですが、企業が独自に算出するのではなく、第三者機関であるESGスコア評価機関が各企業の開示する非財務情報を元に評価・算出を行います。現在世界中では多くの評価機関が存在しており、各評価機関によって評価の基準となる価値観や評価方法が異なります。そのため同じ企業でも、評価機関によってESGスコアが異なるケースがあり、評価のバラツキや公平性の担保といった点において課題であるとの指摘もされています。
| 主なESGスコア評価機関 | 特徴 |
| MSCI | ニューヨークに本拠を置く世界有数の金融サービス企業。業種ごとにESGにおけるリスクマネジメントの程度を分析し算出した「キーイシュー・スコア」から、企業を7段階(AAA〜CCC)で格付けする。 |
| S&P Global | ESGスコアとして最も歴史があり知名度の高いスコアのひとつである「ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス(DJSI)」を提供する。DJSIは、RobecoSAM社が1999年に初めて世界の上場企業を対象に実施したコーポレートサステナビリティ評価(CSA)が基礎データとして使用されている。 |
| Sustainalytics | ESGスコアとして有名な「Sustainalytics ESG Risk Ratings」を提供しており、ESGリスクの度合いを絶対値によるスコアおよび5段階の格付けで評価する。 ESGリスクの度合いはスコアが低い程、低リスク企業であることを示し、スコア0-10はNegligible、10-20はLow、20-30はMedium、30-40はHigh、40以上はSevereに分類される。 |
| ISS ESG | アメリカの議決権行使助言会社であるInstitutional Shareholder Services社が運営し、ESGスコアがA+(持続可能性に優れた企業)からD-(持続可能性に乏しい企業)までの12段階で評価される。業界別で高い評価を受けた企業は「Prime/プライム」評価の認定を受ける。 |
| CDP | 2000年にロンドンで設立された非営利団体で、RE100といった脱炭素社会に向けたイニシアチブの運営機関としての活動も行う。「気候変動」「ウォーターセキュリティ」「フォレスト」の3分野で8段階(A~D⁻)のESGスコアを格付けする。3分野でのA評価獲得は「トリプルA」と呼ばれる。 |
参照:ESG評価機関等の紹介 | 日本取引所グループ (jpx.co.jp)
ESG投資が社会貢献にどう繋がるのか?
ESG投資は社会貢献型投資とも言われ、投資活動が社会貢献に繋がります。企業のESG分野への取り組みは、Eである環境(Environment)に関しては、CO2排出量の削減や資源枯渇対策、環境および水質汚染対策、廃棄物の管理、生物多様性の保全などが挙げられます。 Sの社会性(Social)への取り組みは、人権問題対策や従業員の労働環境の改善、ダイバーシティの受容、地域社会との関係性強化などです。ESG投資のように、ESG分野への取り組みに積極的な企業へ投資をするということは、間接的に企業の社会貢献活動を支援していることに繋がるのです。
今後ESG投資が盛んになり、社会貢献に取り組む企業の株価が高く評価されればESGへの取り組みに注力する企業が増え、世界的課題の解決がより進んでいくという好循環を生みだしていくことが可能になります。
ESG投資リスク
ESG投資は投資であるためリスクが存在します。まずESG投資は、短期間で大きなリターン(利益)を狙って行う投資ではなく、「環境や社会問題に対する取り組み」と言った、短期間では成果が見えにくい点を重視します。そのため、長期的な資産形成に期待できる一方で、短期のリターンは小さくなるリスクがあります。
またESG投資に特有のリスクとして、グリーンウォッシュが挙げられます。グリーンウォッシュとは環境に配慮した企業に見せかけて、実際はそうではない事を指します。 例えば商品やサービスの名称やパッケージデザインに、エコや自然を連想させる要素を盛り込んだり、コーポレートサイトや会社広告などに、環境意識の高さを感じさせる工夫を施したりと様々な方法で少しでもよく見せようと画策します。
グリーンウォッシュのリスクを回避するためには、正しくESGへの取り組みを評価する必要があります。しかしESG経営は、世界的に統一された情報公開の方法やその評価方法などが確立されておらず、今後の大きな課題となっています。
参照:グリーンウォッシュとは?問題点や事例、規制、すぐできる対策を解説:【SDGs ACTION!】朝日新聞デジタル (asahi.com)
ESG投資の未来
財務省が2022年に公表した資料「ESG投資について」によると、近年の消費者(若年層)は、ESG要素に配慮した製品を購入したいと考える傾向が強まっています。 また国内機関投資家の運用総額に占めるサステナブル投資の割合も、2016年には20%以下だったのが、2021年には60%を超えるに至りました。このような状況からもESG投資の市場規模が拡大する勢いは、しばらく衰えないと考えられます。
参照:kyosai20221125-3-2.pdf (mof.go.jp)
反ESG投資の動き
拡大するESG投資ですが、一方で反ESG投資の動きがあります。最も動きが表面化しているのは、ESG投資の主導国でもあるアメリカです。フロリダ州では23年5月にESG投資の活動を制限する「反ESG法」が成立するという出来事が起き、他の州でも動きが見られます。
反ESG投資の動きが起きている要因の一つに、銀行や投資家がESG投資により石油や石炭関連産業への投資を控えている事が、世界的なエネルギー価格の高騰を助長しているとの批判があります。また短期的な利益を得にくいESG投資を進めた投資機関が十分な利益を得られずに、出資者や株主の反発を受けているケースも見られます。一部の反ESGの動きを受けて、ESG投資に慎重な姿勢を示す金融機関や投資家も出始めています。
これら反ESG投資の動きは、ESG投資への揺り戻しと捉える指摘が多く、世界的なESG投資拡大の流れを止めるまでには至っていません。しかし今後さらにESG投資がスタンダードな投資手法となっていくためには、企業の非財務情報の開示基準の整備などを行い、「グリーンウオッシュ(見せかけの環境対応)」やESGスコアの不公平さ等の課題に取り組んでいくことが求められます。
参照:金融による脱炭素推進は曲がり角に差し掛かったか?:米国で高まる反ESGの動き|2023年 | 木内登英のGlobal Economy & Policy Insight | 野村総合研究所(NRI)
ESG投資の今後の課題
ESG投資の拡大に伴い、今後の課題として議論されているのが「ESGスコア」の評価方法です。ESGスコアは、ESG投資先を選定するのに最も重要な指標となり、ESGスコア評価機関が、各企業が公開する非財務情報等をもとにESGスコアの評価・算出を担います。ESGスコアの評価は、評価機関における評価手法にバラツキがあることが、課題として指摘されています。
この評価のバラツキが生じる理由として、各評価機関によって異なる価値観や評価基準に基づいて評価がされている点が影響しているとされています。評価の根本となるESG関連の情報開示に、企業側の制約等がある点も指摘されています。例えばE(環境)スコアは、比較的開示が容易かつ明確な数値化が可能なデータが多く、国際的なガイダンスも先行しているため、スコアのバラツキは起きづらいです。一方でS(社会)スコアは、企業の情報開示の制約や数値化の困難さがスコアのバラツキに影響していると指摘されています。
このような課題を受け、グローバルではISSB(International Sustainability Standards Board、国際サステナビリティ基準審議会)が最初の国際的なESG開示体系として「IFRSサステナビリティ開示基準」の整備を進めています。
国内におけるESGスコア評価基準の整備
日本国内においても、ESGスコアの評価基準を統一的なものにする取り組みが進んでいます。2023年1月に公布、施行された「企業内容等の開示に関する内閣府令」では、企業が公表する有価証券報告書等の記載項目に人的資本・多様性に関する開示を求める規定が設けられました。また、金融庁は2022年12月に「ESG評価・データ提供機関に係る行動規範」を公表しました。そこでESG評価の多様性に関して、「評価の目的、考え方、基本的方法論等を明らかにすることが重要であり、これらに沿った評価が行われている場合には評価結果が機関によって異なることは必ずしも問題ではない」としました。評価の基準となる価値観や評価方法が異なること自体は問題視せず、それらについて十分に開示が行われている事が重要であると提言をしています。
参照:GPIFの「ESG活動報告」から見るESG投資の課題 | SOMPOリスクマネジメント (sompo-rc.co.jp)
まとめ
ここまで、ESG投資の近年の動向と今後の展望について紹介しました。
ESG投資額はここ数年で数倍に拡大しており、今後もその流れは続くと見られます。投資手法のスタンダードとなる為に、ESGへの取り組みをグローバルな統一基準で評価出来るような仕組み作りも進んでおり、企業価値を決める要素にESGが重要となっていくでしょう。