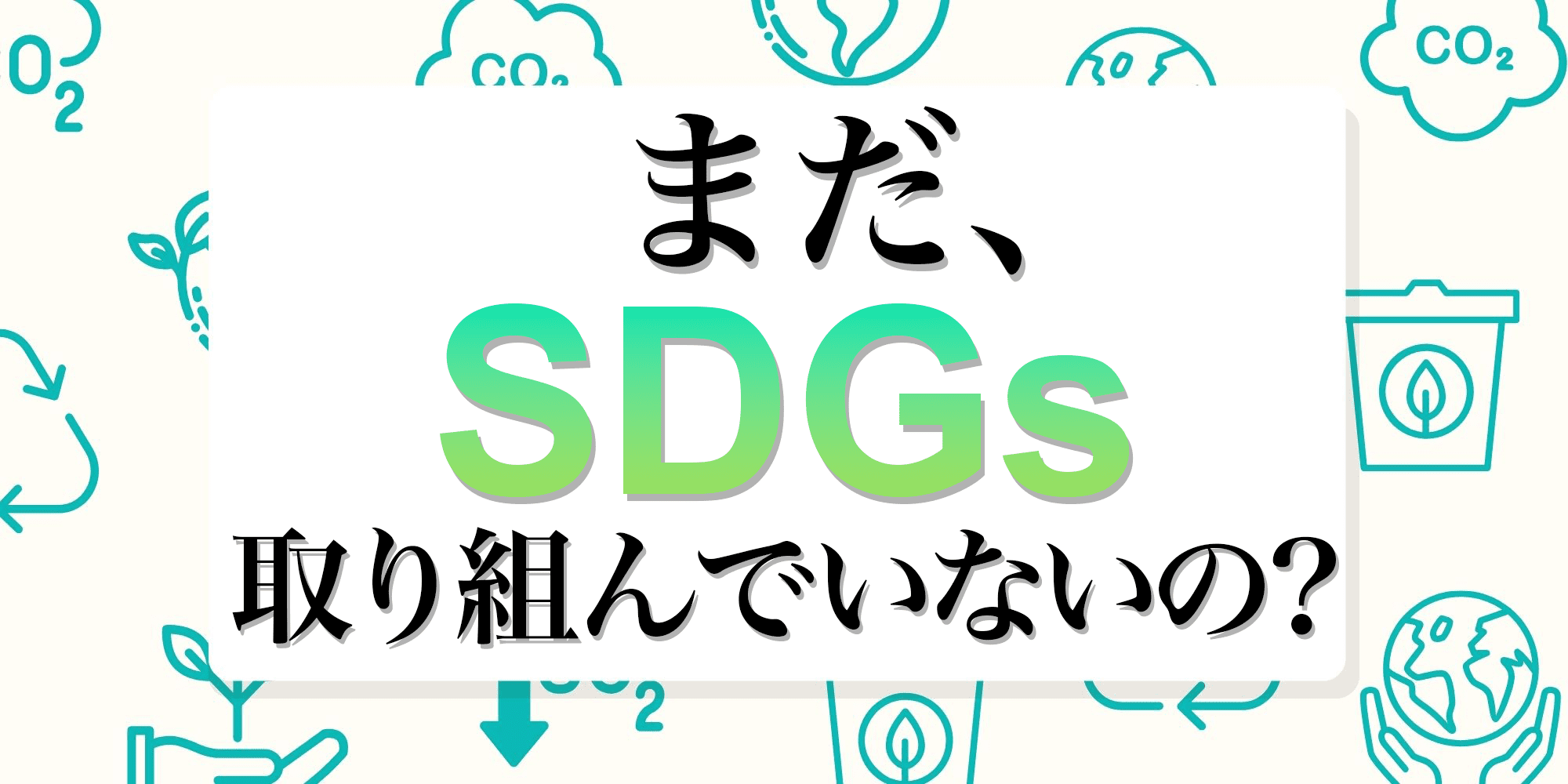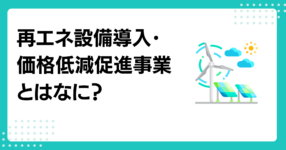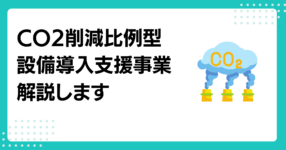SDGs(Sustainable Development Goals)は、「持続可能な開発目標」と訳される言葉で、世界で取り組むべき17の目標を明確にしたものです。
具体的には、貧困や健康、教育などのさまざまな分野で取り組みが進められています。
「SDGsに向けて、私たちには何ができるのだろう?」と考えたことのある方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回の記事では簡単に実践できるSDGsの方法を3つ紹介しています。
さらに、企業がどのようにSDGsに取り組んでいるのか、未来の日本がSDGsを達成することでどう変わるのか、これらの疑問にも答えていきます。
SDGsは遠い未来だけでなく、私たちの現在の生活にも深くに関わっています。
この記事を通じて、あなたが取り組みやすいSDGsの実践方法を見つけてください。
今すぐ簡単にできる「SDGs」の実践方法3選

早速ですが、今からすぐに取り組めるSDGsの実践方法を3つ紹介します。
- 地産地消を支持する
- 節水と節電を意識する
- マイバックやマイボトルを使用する
地産地消を支持する
地産地消は、地元で生産された農産物や製品をその地域で消費する考え方を指します。
非常にシンプルですが、SDGsの実現に向けた大切な取り組みの一つです。
さらに、地元で作られた農産物を購入することは、地域経済の活性化や農家の支援といった、持続可能な経済を作り出すことにもつながります。
SDGsの目標2は、「飢餓をゼロに」です。
地産地消の取り組みをすることで、新鮮で栄養価の高い食材を入手できるうえに、目標2の実現にも大きな役割を果たします。
SDGsに向けて何から手をつけていいのか迷ったときは、地産地消から始めてみてはいかがでしょうか。
まずは、地元の農産物市や地域の食材を取り扱うお店を訪れてみてください。
節水と節電を意識する
節水と節電は、私たちの日常生活の中で手軽に始められるSDGsの実践方法の1つです。
また、家を出るときに忘れずに電気を消すことや、冷暖房の温度を適切に設定することによって、電気の使用量を削減することも可能です。
これらの取り組みは、水やエネルギーといった資源の無駄遣いを減少させることにつながります。
SDGsの目標の中には、「安全な水とトイレを世界中に(目標6)」や「誰もが使えるクリーンエネルギー(目標7)があります。
水やエネルギーの無駄遣いを減らす、日常の小さな行動の積み重ねが、SDGs達成の第一歩になるのです。
マイバックやマイボトルを使用する
マイバックやマイボトルの使用は、プラスチック廃棄物の削減につながります。
私たちの生活には、プラスチック製品が多く存在しています。
特に、使い捨てのプラスチック製品は、現代社会の抱える大きな環境問題の1つです。
プラスチックは、分解されるのに何百年もの時間が必要です。
一度、プラスチック製品が作られてしまうと、長い間、環境を汚染し続けます。
また、海洋中のプラスチック廃棄物は、生態系への大きな影響を及ぼしています。
日本国内でも、絶滅危惧種のウミガメがプラスチック製のレジ袋を食べて死んでしまったという事件もありました。
参照:絶滅危惧のウミガメ、腹からレジ袋 死んだ状態で発見:朝日新聞デジタル
SDGsの目標14は、「海の豊かさを守ろう」です。
今回のウミガメの事件は、私たちがレジ袋を海に捨てなければ起こりませんでした。
各企業での取り組み

それでは、実際に企業ではSDGsに向けてどのような取り組みが行われているのでしょうか。
今回は、誰もが知る有名な2つの企業での取り組みを紹介します。
- 株式会社ユニクロ
- 任天堂株式会社
株式会社ユニクロ
ファッション業界の大手企業であるユニクロは、SDGsに向けてさまざまな取り組みを行っています。
特に、SDGsの目標12「つくる責任 つかう責任」における取り組みが、ユニクロならではの特別なものになっています。
このプロジェクトでは、購入された服がいずれ再利用されるという考え方を基に、環境にやさしい循環型のファッションビジネスを推進しています。
まずは、ユーザーから不要になった服を回収します。
回収には、ユニクロの各店舗に設置されている「RE.UNIQLO回収ボックス」を使っています。
その後、回収した服は適切に仕分けられます。
例えば、服の状態がよく、そのまま利用できるものは、難民の元へ送り届けます。
リユースが難しい服の場合は、CO2を削減できる代替燃料にリサイクルされます。
これにより、資源の無駄を大幅に削減し、環境への影響を軽減しているのです。
参照:RE.UNIQLO:あなたのユニクロ、次に生かそう。 | 服のチカラを、社会のチカラに。 UNIQLO Sustainability
任天堂株式会社
任天堂は、製品開発からオフィスでの業務に至るまで、SDGsに向けて幅広い取り組みを行っています。
例えば、目標13「気候変動に具体的な対策を」に対処するため、任天堂はCO2の排出を削減するための取り組みを進めています。
さらに、エネルギー効率を向上させるために、ゲーム機に待機モードやスリープモードを導入しています。
大人気のゲーム機種「Nintendo Switch」においても、開発が進められ、エネルギー効率が年々良くなっています。
その結果、初期の製品と比べて、消費電力が大幅に減少しています。
商品の輸送に関しても、任天堂は環境にやさしい方法を採用しています。
欧州任天堂では、港から倉庫への商品輸送をトラックではなく、鉄道で行っています。
これにより、最大85%のCO2の削減が可能になりました。
また、オフィスでも環境に配慮した取り組みが進められています。
例えば、新しい事業所を設立するときは、高効率の空調や照明、再生可能エネルギーの導入などの環境にやさしい設備を取り入れています。
参照:環境:さまざまな側面で環境負荷低減に取り組みます。 ゲームプレイ時の消費電力|CSR情報|任天堂
SDGsでこれからの日本はどうなるのか?

SDGsの取り組みが進んでいくと、日本はどうなるのでしょうか。
考えられるのは、次の3つの素敵な未来です。
- 化石燃料から再生可能エネルギーへシフトする
- すべての人が活躍できる社会になる
- 子どもたちの教育変革が進む
化石燃料から再生可能エネルギーへシフトする
今後、日本では化石燃料から、太陽光や風力といった再生可能エネルギーへと移行する動きが活発になると考えられます。
これは、目標13「気候変動に具体的な対策を」に向けた代表的な取り組みの1つです。
化石燃料の燃焼は、大量にCO2を排出します。
このCO2は、地球温暖化を引き起こす最大の要因とされています。
さらに言うと、私たちが日常で目にする異常気象や豪雨、猛暑などは、地球温暖化が影響していると考えられています。
もしかすると、再生可能エネルギーが化石燃料のように利用される未来は、そう遠くないのかもしれません。
すべての人が活躍できる社会になる
SDGsの取り組みによって、日本はすべての人が活躍できる社会になると考えられます。
その根拠は、SDGsの目標5「ジェンダー平等を実現しよう」、目標10「人や国の不平等をなくそう」にあります。
平等が実現すると、性別や年齢、出身地などを背景に差別を受けていた人々が、社会で活躍できるようになります。
つまり、さまざまな価値観や経験を持つ人々と一緒に考える機会が増えるということです。
様々な人が集まり、共に考え、行動することで、日本が抱えている問題へのよりよい解決策や新しいアイディアが生まれやすくなります。
子どもたちの教育変革が進む
SDGsによって、子どもたちの教育にも大きな変化があるといわれています。
SDGsの目標4が、「質の高い教育をみんなに」であるためです。
日本は、多くの人が義務教育を受けることができる裕福な環境にありますが、質の高い教育を目指すための様々な取り組みが進められています。
その一例として、最近ではSDGsに関する内容が教育カリキュラムに取り入れられるようになりました。
例えば、小学生向けにSDGsを学ぶボードゲームが開発され、多くの小学校で導入されています。
参照:【公式】子どもと大人のSDGs学習ゲームGet The Point
また、食に関する教育、通称「食育」も学校の授業の一部として取り入れられるようになりました。
食育では、子どもたちが持続可能な食文化や食の価値について学習します。
さらに、フードロスの問題も取り扱っているため、子どもの頃から食べ物を大切にしようという考え方を学べるようになっています。
これらの教育内容は、子どもたちが将来、社会の一員としてSDGsの目標に向かって行動する力を身につけるための土台となります。
まとめ
SDGsと聞くと難しそうに感じますが、今すぐできる実践方法はたくさんあります。
特におすすめなのが、次の3つです。
- 地産地消を支持する
- 節水と節電を意識する
- マイバックやマイボトルを使用する
また、SDGsに向けた取り組みが進められると、日本はさらに良い国になると考えられます。
具体的には、CO2を排出しないエネルギー供給を行ったり、差別のない平等な社会を実現したり、子どもたちがよりよい教育を受けられるようになったりすると言われています。
特に、CO2は地球温暖化の最大の原因です。
そのため、CO2削減をするための取り組みが世界中で進められています。
日本でも、CO2を大幅に削減できた企業は、株主などから高い評価を受けられます。
まだCO2削減の取り組みを行っていない場合は、照明をLEDに切り替えるなどの簡単な実践から始めましょう。
CO2削減に向けた取り組みを始める前に、まずは現在のCO2排出量を把握するべきです。
具体的に何キロのCO2を削減できたのかなどの成果がわからなくなるためです。
弊社では、CO2排出量を無料で計算するサービスを提供しています。
無料で利用できますので、ぜひご活用ください。
著者のプロフィール
- 小学校教員として、カーボンニュートラルや脱炭素に関する授業を行った経験がある。子どもたちが理解できるように、専門用語を分かりやすく、かみ砕いて説明することを心がけた。この経験を活かし、脱炭素化の重要性を広く伝えるために、誰にとっても理解しやすい記事を作成している。