SDGsには17の目標があり、持続可能な社会の実現のために解決すべき課題が提示されています。中でも、目標7と目標13は深刻化する地球温暖化を解決するために、緊急の目標だといわれています。目標7と目標13は、再生可能エネルギーへの移行を推奨する内容となっていて、最近注目されている脱炭素・カーボンニュートラルと深く関わるテーマでもあるのです。
今回は、再生可能エネルギーでSDGsの目標7と13を達成する仕組みや事例を解説していきます。どうぞ、最後までお付き合い下さい。
再生可能エネルギーとSDGsの目標7

SDGsの目標7

”Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all”
すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する
出典:JAPAN SGDs Action Platform – 外務省

国際連合広報センターによると、2020年の時点で世界で電気が使えていない人の数は7億人もいるといいます。電気が使えて当たり前の私たちから見ると信じられないデータです。また、電気が使えていても非効率的な方法(不便な方法)であったり、汚染につながる方法であったりと、十分な設備機器が備わっていない人が24億人です。
かつ、持続可能な再生可能エネルギーで電力が確保できている人は世界全体の17%程度にとどまっている、と報告されています。つまり、SDGsの目標7の達成率は現在17%程度であることがわかります。そこで、SDGsでは急がねばならない目標として、3つの課題を打ち出しています。
参照:持続可能な開発目標(SDGs)- 国際連合広報センター
目標7の3つの課題とゴール
目標7の3つの課題とゴールをまとめていきます。
目標7-1:2030年までに現代エネルギーサービスを普及させる
電力の普及率が低い地域・国の1つがアフリカです。南アフリカなど、ほんの1部の国を除いて、サブサハラ・アフリカでは長期的な経済停滞と貧困に苦しんでいます。56諸国のほとんどの国で、電力の普及率は30%以下に留まります。電気が使えないことが大問題となる先進国と、電気が使えないことが日常となっている途上国との格差が大きすぎると問題視され、先進国からの支援を求めています。
目標7-2:2030年までに再生可能エネルギーの比率を拡大させる
もう1つの目標は、SDGsではエネルギーミックスを構成する電源のうち、再生可能エネルギーの比率を高めることです。通常、多くの国では石油・石炭・ガス、原子力、再生可能エネルギーと様々なエネルギー源が使われています。このように複数の方法で電力構成することをエネルギーミックスといいます。
目標7-3:2030年までに世界全体のエネルギー効率を倍増させる
エネルギー効率とは、一定の電力で出来ることの大きさや時間のことをいい、kW/hという単位で表します。例えば、電子レンジが1時間使える場合1kW/h。エネルギー効率が倍増すれば、同じ1kWの電力でも電子レンジが2、3時間使えるようになります。もう1つ、エネルギー効率でよく使われるのが、電力にかかるコストから効率を計る方法です。コスト対効果が高くなるほど、エネルギー効率も高くなるのです。
再生可能エネルギーでどんな対策ができるのか
最も代表的な目標7への対策は、企業・個人が再生可能エネルギーの料金プランを利用したり、再エネ設備を導入する方法です。ただ、目標7-1のように、電力が使えないアフリカ諸国の問題に、個人や企業ができることは限られてしまいます。問題が大きすぎるからです。方法として途上国が発行するカーボンクレジットを購入すれば、途上国への支援につながり、かつ企業自身の再エネ比率の向上にもつながります。

「2国間クレジット」に関する情報はこちらから:JCM – 経済産業省
もともと、カーボンクレジットを経済格差が大きい途上国を支援するために、京都議定書にて制定された再エネ導入の枠組みです。日本では、「2国間クレジット」といって行政が発行するクレジットを購入することが可能です。他にも、エアコンの温度調整や省エネ電化製品の利用にてエネルギー効率を上げたりと、SDGsに加担することができます。
SDGsとはそもそも何なのか、概要を知りたい方は下記のリンクからご覧頂けます。
関連記事はこちら:カーボンニュートラルとSDGsの関わりとは?事例も解説
再生可能エネルギーとSDGs目標7の事例
SDGsの目標7と再生可能エネルギーの導入事例は、豊富な情報がネットで探せますので、当記事ではアフリカ支援と再エネに視点をあてて事例を紹介しましょう。
Panasonicの太陽光発電設置や良品生活の手工業商品開発など、多くの大手企業でアフリカ支援を行っています。海外への進出は中小企業にとっては、ハードルが高く感じるかもしれません。経済産業省やJETRO・JICA・UNDPなど企業のアフリカ支援をサポートする機関がいくつかあります。
屋根業者から太陽光発電、アフリカ支援に展開:Kens Co.Ltd
佐賀県鳥栖市の太陽光発電パネル業者「Kens Co. Ltd」は、「川口スチール工業」の3代目である川口氏が、分社として設立した太陽光パネル専門のメーカーです。「川口スチール工業」はもともとは屋根業者で、薄型太陽光発電の開発に成功したことで注目されています。
代表である川口氏は、電気の普及率が低いアフリカに太陽光パネルで貢献したい、という思いから太2018年に日本政府企画のアフリカ支援実証プロジェクトに参加しています。このプロジェクトで、ナイジェリアを中心に学校や建物の屋根や街灯に太陽光パネルを設置しました。将来的には、アフリカの太陽光発電市場で拡販していく計画です。

川口氏のアフリカ支援プロジェクトは以下の3つの柱で構成されています。
- 全国の企業・工場の屋根に無償で太陽光発電を設置
- 創出した再エネをパートナー企業に売電
- 利益から屋根の賃料をの一部を還元、途上国への太陽光パネル設置を支援
そもそも、電気が通っていない地域が大半であったため、パネルで創出した電気をランタンに充電して学校や住宅で活用したとのことです。現在でも、川口氏はパートナー企業を募りながら、アフリカにおける太陽光発電の普及拡大に努めています。2020年にはForbes Japan主催の「SMALL GIANTS AWARD」でグランプリを受賞しています。
参照:2018年度アフリカビジネス実証事業実施報告書 – JETRO
再生可能エネルギーとSDGsの目標13

次に、再生可能エネルギーと深く関わるもう1つのSDGs、目標13について解説していきます。
SDGsの目標13

Take urgent action to combat climate change and its impact
~気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる
出典:JAPAN SGDs Action Platform – 外務省

2023年6月、集中豪雨が九州地方を襲い、7月には秋田県で豪雨による土砂被害、浸水が拡大しました。欧州や北米は過去最高の熱波を記録し、カナダでも自然発火による森林火災が数日間続きました。これまでにない規模・頻度で、世界では熱波や干ばつ、豪雨に台風と自然災害が相次いでいます。これらの自然災害は、地球温暖化による気候変動が要因であることが科学的に実証されています。

地球温暖化を引き起こすのは、人の社会活動・経済活動から生じるGHG(温室効果ガス)です。このまま地球の気温が上昇し続けた場合、海水温の上昇と氷河の融解から海面が上昇し、さらなる大規模水害を引き起こすリスクがあります。水不足の地域では、干ばつが進行し破壊的な砂嵐にてさらに干ばつを拡大させる恐れがあるのです。SDGsでは、地球温暖化を食い止めるために緊急な対策が必要だとしています。
目標13の3つの課題とゴール
目標13の3つの課題とゴールを見ていきます。
目標13-1 すべての国で自然災害にたいする適応力を強化する
いざ自然災害が起きた時の被害を最小限に抑えるために、SDGsではすべての国において緊急で対応できるよう備えておくことを推奨しています。例えば、世界気象機関(WMO)は気象観測・調査を行い、自然災害の早期警報を実施する機関です。各国において、気象情報を迅速に交換できる仕組みや気象観測結果や統計を統一して発表する仕組みを備えることで、自然対策への適応力が高まるとしています。
目標13-2 それぞれの国で気候変動への対策を政策として計画する
また、目標13を達成するためには課題として、それぞれの国で気候変動を解決するための政策・戦略・計画を立てることを挙げています。日本の目標は、2030年までにGHGを46%削減、2050年にカーボンニュートラル(GHG実質ゼロ)です。そのために、助成金や税制優遇を制定して、再生可能エネルギーの導入の促進をはかっています。また、世界全体で対策が立てれるよう、先進国は途上国への支援策も設けています。
目標13-3 気候変動の進行を緩めるための教育・啓発を促進させる
気候変動を抑えていくためには、地球温暖化に対する理解が必要です。地球温暖化を引き起こす要因が理解できれば、すべき対策が見えてきます。理解するための教育・啓発を国策として進めていく必要があるのです。SDGsでは、各国が地球温暖化の教育制度への取り組みを奨めています。
関連記事はこちら:カーボンニュートラル税制(CN税制)とは
再生可能エネルギーでどんな対策ができるのか
気候変動を解決するために、最も有効だとされているのが、化石燃料から再生可能エネルギーへの移行です。再生可能エネルギーとは、「自然環境から容易に入手可能」「CO2を排出しない」「持続可能(永続的に使える)」といった要素を持つエネルギーのことです。
代表的な再生可能エネルギーには「太陽光」「風力」「水力」「地熱」「バイオマス」「水素/アンモニア」などがあります。再生可能エネルギーを導入する方法は、「発電設備を購入する」以外にも、ガソリン車からEVに移行、電気料金プランを再エネに変更、再エネで製造された製品を購入、再エネ証書を購入するなど、様々な方法を取り入れることが可能です。
関連記事はこちら:農業分野のJクレジット制度
再生可能エネルギーとSDGs目標13の事例
再生可能エネルギーの設備機器の導入は、いくらコストは低下しているとはいえ、決して安価だとはいえません。一定以上の消費電力を再エネで得るためには、数十万~数百万円のコストがかかってしまいます。そこで手始めに検討したいのが、手軽に入手できる工事不要の小型太陽光パネルや太陽光で発電するLEDライトです。数万円程度で、駐車場や敷地内、ベランダや屋上、窓際など簡単に設置できます。
小型太陽光パネルやLEDライトで再エネ
新電力会社やローカルの太陽光発電業者では、マンションのベランダに設置できる小型太陽光パネルやLEDライト、再エネ電力プランなどを提供しています。10万円以下でも200W~400W程度の発電が可能で、小型発電機に接続すれば、PCやプリンター、その他電気機器の電源として使えます。太陽光で点灯するLEDライトなどオンライン通販では数千円です。
参照:ベランダ発電 自作・太陽光発電システム – KURASHI工房
まとめ

再生可能エネルギーの導入、利用を進めることは、今回解説したようにSDGsの目標7と13のダイレクトな解決につながります。加えて、目標7と13の課題解決は、そこから途上国の経済成長につながったり、自然環境保全につながったりとその他のSDGsの目標達成にもかかわってくるのです。この点が、1企業の1つのアクションが重要だといわれる所以です。
「小さな企業だから」「小さな対策だから」効果はないだろう、やっても変わらないだろうと、モチベーションが見いだせない方もいるかもしれません。しかし、「小さな対策」であっても100企業、1000企業、1億人が行えば、それはこの上なく巨大な効果を生み出します。
地球温暖化を一刻も早く改善していくためには、「小さな対策だけど、役に立つかもしれない」と実践していくことが、今強く求めらているのです。ぜひ、この機会に何か1つ、企業・個人としてできることを実践していきましょう。
また、無料のタンソチェックツールでは、自社で発生するCO2排出量を測定することが可能です。簡単なアカウント登録でご利用いただけますので、併せてご活用下さい。
著者のプロフィール

- 太陽光発電・蓄電池等を専門とする住宅設備会社での勤務歴10年。再エネの専門知識からエネルギー系の株式投資と記事執筆を開始する。エネルギー専門の投資家兼ライターとして独立して7年。過去にNY、ロンドンの移住歴あり、国内・海外メディアを駆使した情報収集が強み。
最新の投稿
 CO2削減2023年10月21日【在宅VS出社】在宅ワークがカーボンニュートラルを加速させる理由とは
CO2削減2023年10月21日【在宅VS出社】在宅ワークがカーボンニュートラルを加速させる理由とは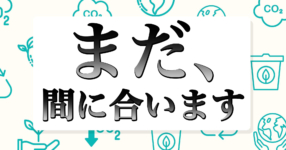 CO2削減2023年10月17日【まだ間に合う】企業がCO2見える化する一番大きなメリットとは?ソフトウェアアプリのデメリットも紹介
CO2削減2023年10月17日【まだ間に合う】企業がCO2見える化する一番大きなメリットとは?ソフトウェアアプリのデメリットも紹介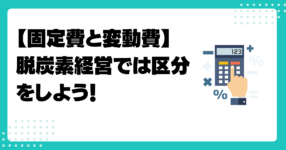 第6章2023年12月16日【固定費と変動費】脱炭素経営では区分するところから始まる!脱炭素会計の基本
第6章2023年12月16日【固定費と変動費】脱炭素経営では区分するところから始まる!脱炭素会計の基本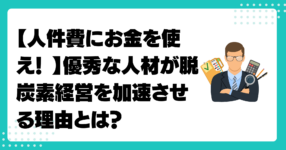 第6章2023年12月16日【人件費にお金を使え! 】優秀な人材が脱炭素経営を加速させる理由とは?GX人材の需要
第6章2023年12月16日【人件費にお金を使え! 】優秀な人材が脱炭素経営を加速させる理由とは?GX人材の需要
