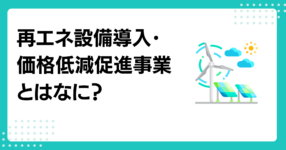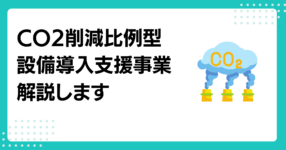SDGs(持続可能な開発目標)は、今や多くの企業が取り組む重要なテーマとなっています。
特に中小企業にとって、SDGsへの取り組みは、新規顧客の獲得や他社との差別化を行う大きなチャンスです。
しかし、「どうせなら、面白い取り組みがしたい!」と思う方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回の記事では、大手から中小企業、さらには海外企業まで、SDGsの面白い取り組みをピックアップして多数紹介します。
企業の面白い取り組み3選

早速、企業の面白い取り組みを3つ紹介します。
今回、紹介するのは下記の3社です。
- ANA
- ⽊内酒造株式会社
- ネスレ日本株式会社
ANA
ANAグループは、SDGsの取り組みとして、「ANAアップサイクルプロジェクト」を行っています。
このプロジェクトでは、「ANA特製ルームシューズ」が製造されています。
シートカバーは、飛行機内の乗客の安全を考慮して定期的にクリーニングや交換が行われます。
この交換後のシートカバーを再利用する方法を考え、生み出されたのがルームシューズにするという斬新なアイデアでした。
また、使い勝手にもこだわりを持っています。
ルームシューズは日本で最も多くのスリッパを生産している山形県の工場で、熟練の職人が手作りしています。
そのため、スリッパとしても利用可能です。
参照:ANA アップサイクルプロジェクト第1弾 オンワード商事(株)とのコラボ!「ANA特製ルームシューズ」販売開始|プレスリリース|ANAグループ企業情報
⽊内酒造株式会社
⽊内酒造株式会社は、日本のクラフトビールの代表として、50カ国以上で知られています。
木内酒造では、廃棄されるビールを再利用した取り組み「SAVE BEER SPIRITS」を行っています。
きっかけは、コロナ禍で、多くの飲食店は大量の未使用のビールを廃棄せざるを得ない状況でした。
⽊内酒造は、賞味期限が迫るビールを無料で蒸留し、新しいクラフトジンとして再生させることに成功しました。
さらに、「BREWERIES UNITE FOR IBARAKI」というプロジェクトも開始しています。
工場で余ってしまったビールを活用し、⼿指消毒用の高濃度エタノールも製造しました。
参照:【茨城県】⽊内酒造株式会社 〜SDGsを経営のヒントに、持続可能な酒造りを⽊内酒造から世界へ〜
ネスレ日本株式会社
ネスレ日本株式会社は、日清紡グループの一員であるニッシントーア・岩尾株式会社と手を結び、SDGsの取り組みとして面白いプロジェクトを開始しました。
具体的には、アップサイクルによる、衣服の製作です。
まず、紙製の詰め替え容器を繊維に変換します。
そして、コーヒーを抽出した際の残りかすを染料として再利用します。
この繊維と染料を用いてTシャツやエプロンを製造するという取り組みです。
繊維をコーヒーで染色する技術は、業界初の偉業でした。
さらに、日清紡グループは、再利用された繊維や染料を使用した製品をアパレルメーカーに供給しようとしています。
参照:廃棄される紙パッケージとコーヒー残渣に新たな命を吹き込む、業界初の試み | ネスレと日清紡、“アップサイクル”衣服の製作を開始! | ~「ネスカフェ」の空きパッケージを回収する拠点も設置~
中小企業だからこそ、SDGsに取り組む2つのメリット

廃棄されるシーツやビール、コーヒーの残りかすなどを再利用して製品を作る面白い取り組みが国内の企業で行われています。
しかし、中小企業が苦労をしてまでSDGsに取り組むメリットはあるのでしょうか。
今回は、代表的な2つのメリットを紹介します。
- 他社との差別化
- 地域密着型の取り組みが可能
他社との差別化
中小企業がSDGsに取り組み、他社との差別化を図ることは非常に重要です。
なぜなら、消費者の意識や価値観が変化しているからです。
そのため、SDGsへの取り組みは企業の魅力を高め、消費者の心を掴むための大きな武器となるのです。
特に中小企業は、大手企業と比べて、組織全体で動ける柔軟さがあります。
SDGsを取り入れることで、大手企業よりも先に新しい市場を獲得できる可能性を秘めているのです。
中小企業がSDGsに取り組むことで、今までとは異なる市場の開拓や、企業ブランドの魅力を高めることができます。
その結果、競争力の向上や新しい顧客の獲得につながることが期待できます。
地域密着型の取り組みが可能
中小企業が持つ最大の魅力の1つは、地域との強い結びつきです。
大手企業が全国や世界規模での事業展開を重視するのに対し、中小企業は特定の地域やコミュニティに深く根付いていることが多いです。
この地域性は、SDGsに取り組む際の大きなメリットとなり得ます。
中小企業は、その地域の文化や歴史、そして住民のニーズや課題を熟知しています。
これは、SDGsに関連する取り組みを地域に合わせて行うためには欠かせません。
例えば、地域の資源や特産品を活かした持続可能な商品開発や、地域の課題を解決するためのプロジェクトを立ち上げることが考えられます。
さらに、地域密着型の取り組みは、企業のストーリーとして消費者に伝わりやすいです。
消費者は、商品やサービスの背景にある熱い物語に興味を持っています。
海外のちょっと変わった取り組み

国内でもSDGsに向けて、様々な取り組みが行われていました。
しかし、海外ではどうなのでしょうか。
ここからは、海外のちょっと変わったSDGsの取り組みを2つ紹介します。
- Bird(アメリカ)
- Boody(オーストラリア)
Bird(アメリカ)
アメリカの「Bird」は、電動スクーターのシェアリングサービスを行っています。
このサービスの裏側に面白い仕掛けが隠されており、それがSDGsの取り組みの成功例として注目されています。
電動スクーターのシェアサービスにおける最大の問題は、使用後に正しく返却されないことでした。
これを解決したのが、「チャージャー」という新しいアルバイトです。
チャージャーは、路上に放置されたBirdのスクーターを回収・充電して、再度利用できる状態にします。
また、チャージャーは、アプリ上のマップを参考にして、充電が必要なスクーターを探します。
そのため、まるで『ポケモンGO』のように、ゲーム感覚でアルバイトを楽しむことができ、多くの若者たちに支持されています。
参照:シリコンバレー101(756) ポケモンGO感覚の報酬システムでシェア電動スクーターの充電問題を解決 | TECH+(テックプラス)
Boody(オーストラリア)
オーストラリア発のブランド「Boody」は、竹を利用して衣服を製造しています。
竹は、環境にやさしいと言われています。
その理由は、他の植物よりも成長に水を必要とせず、雨水だけで十分に育つためです。
さらに、竹林は、森林よりも二酸化炭素を吸収しつつ、30%も多くの酸素を供給します。
Boodyは、このような竹の特性を活かし、持続可能な製品作りを続けています。
また、少ない環境負荷で高品質な衣服を販売している結果が高く評価され、数々の認証や認定を受けています。
SDGsを実践した企業の成功例

ここからは、SDGsを実践した企業の成功例を3つ紹介します。
- 株式会社SAMURAI TRADING
- ウォータースタンド株式会社
- 株式会社TBM
株式会社SAMURAI TRADING
株式会社SAMURAI TRADINGは、業務用デザートの生産で廃棄される卵の殻を利用して、バイオマスプラスチック「PLASHELL」を開発しました。
さらに、卵殻を利用した紙製品「CaMISHELL」や、卵殻比率が55%のバイオマス素材「Shellmine」も開発されました。
このバイオマス素材は、大手外食チェーンや大手ホテルチェーンでも使用されています。
さらに、「エコ卵プロジェクト」というSDGsの普及活動を立ち上げました。
ここでは、自治体と協力し、廃食油のアップサイクルを行っています。
参照:【埼⽟県】株式会社SAMURAI TRADING 〜卵殻を利活⽤した廃棄物削減・CO2削減の実現に貢献〜
ウォータースタンド株式会社
ウォータースタンド株式会社は、浄水型ウォーターサーバーのレンタルと空気清浄機のレンタルを手がけています。
SDGsの取り組みとして、自治体や他の企業と協力し、「ボトルフリープロジェクト」を実施しています。
このプロジェクトでは、マイボトルの使用を呼びかけ、使い捨てのプラスチックボトルを減らそうとしています。
マイボトル使用を呼びかけつつ、2022年6月までに8万1000本の水筒を配布しました。
さらに、61の地方自治体と連携して、誰もが給水できるウォータースタンドを1669台も設置しました。
また、教育機関でのSDGsに関する出前授業や、自治体が開催するSDGs関連のミーティングなどでの発言の機会も増えてきました。
参照:【埼⽟県】ウォータースタンド株式会社 〜2030年までに使い捨てプラボトル30億本削減に取り組む〜
株式会社TBM
株式会社TBMは、環境にやさしい新素材「LIMEX」を開発しました。
この素材は、プラスチックや紙の代替として注目を浴びています。
LIMEXは、石灰石を主原料とし、石油や水の消費を抑える特性があったからです。
また、2022年には、横須賀工場を建設し、使用済みLIMEXや廃プラスチックのリサイクルを始めました。
地域社会と連携し、アップサイクルモデルの構築も進めています。
参照:株式会社TBM 〜世界が注⽬する⾰命的新素材「LIMEX(ライメックス)」を開発〜
まとめ
SDGsへの取り組みを行うことで、中小企業は地域密着型の取り組みなどで大手との差別化を図ることが可能です。
これにより、競争力の向上や売上アップが期待できます。
それから、海外の企業も独自の方法でSDGsに取り組み、数多くの成功を収めています。
あなたの企業でも、企業の成功例を参考にSDGsに向けた取り組みを始めましょう。
とはいえ、何から手を付けていいのか分からない方も多いはずです。
そこで、まずは自社のCO2排出量を調べてみてはいかがでしょうか。
弊社は、CO2排出量を無料で計算するサービスを提供しています。
SDGsに向けた第一歩として、ご利用ください。
著者のプロフィール
- 小学校教員として、カーボンニュートラルや脱炭素に関する授業を行った経験がある。子どもたちが理解できるように、専門用語を分かりやすく、かみ砕いて説明することを心がけた。この経験を活かし、脱炭素化の重要性を広く伝えるために、誰にとっても理解しやすい記事を作成している。