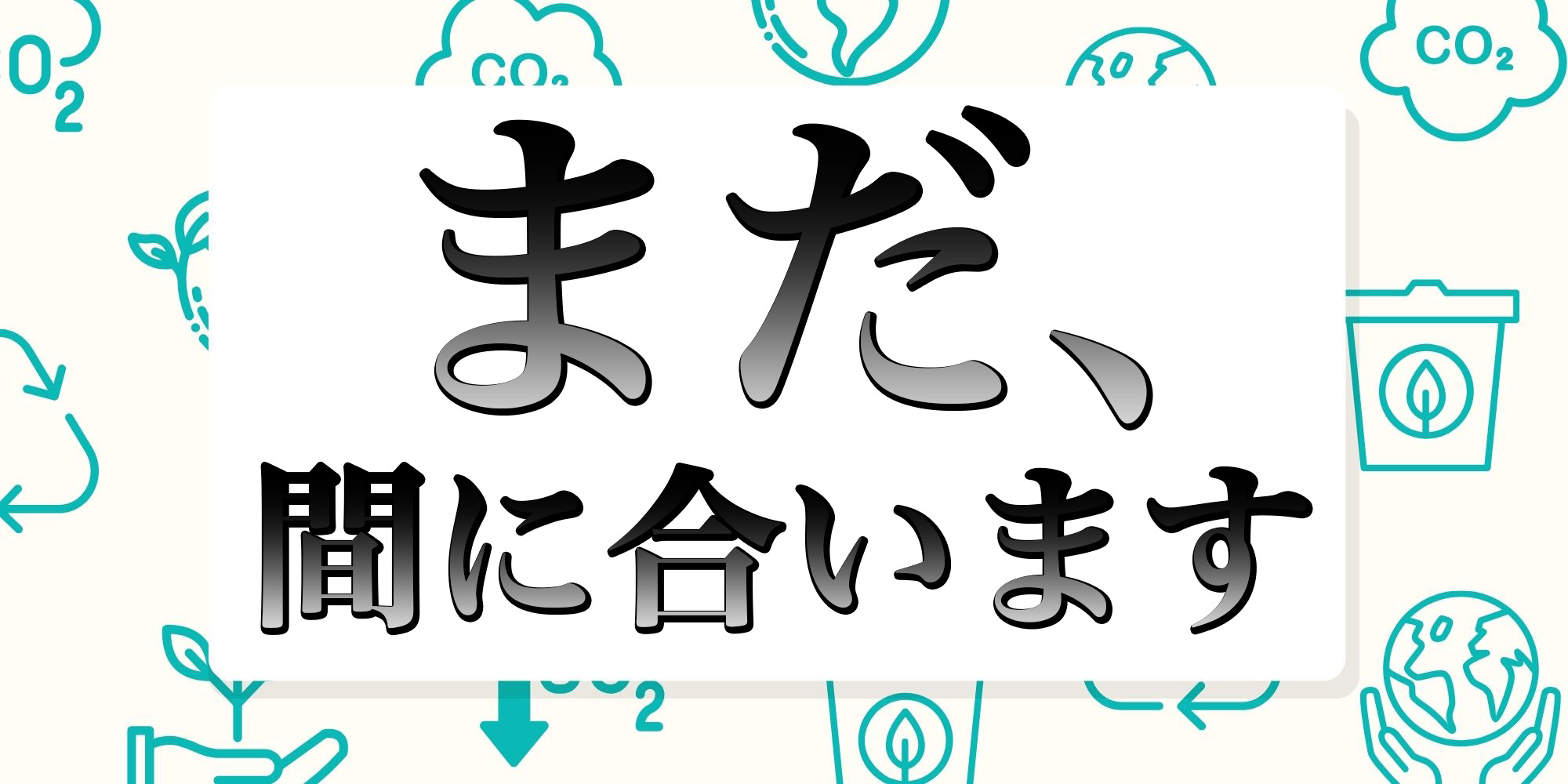脱炭素は、いよいよ中小企業にとっても避けられないとの認識が広まる中、自社のCO2排出量をまだ把握していないケースもあるようです。
いったいどれくらいに及ぶのか、そもそもどうやって測るものなのか、と戸惑った時に検討したいのがソフトウェアを活用したCO2の見える化です。
見える化は、CO2削減に取り組みやすくなるだけでなく、企業にとって数々のメリットがあります。
今回は、CO2見える化を実施するメリットや見える化にあたっての準備などを解説していきます。
結論:CO2見える化で、売上向上を図ることができる

その理由を解説していくにあたって、まずは、最初にCO2の見える化とは何かを簡単に見ていきましょう。
CO2の見える化とは
CO2の見える化とは、商品やサービスのすべての過程、事業活動全体におけるCO2排出量をグラフや図表などで可視化することです。
ここで言うすべての過程とは「商品やサービスの材料調達から生産・廃棄・リサイクルまでの一連の流れ」を指します。
CO2見える化のイメージ
事業活動全体で排出するCO2は、Scope1、2、3で分類されています。
- Scope1 → 自社で直接的に排出するCO2(製造・生産で生じるもの)
- Scope2 → 他社から入手して間接的に排出するCO2(電力、ガスなど)
- Scope3 → 取引先、従業員、顧客など社外で排出するCO2(通勤の燃料など)
CO2見える化のやり方・方法
脱炭素経営は、まず自社のCO2排出量を知ることから始まると言われています。
しかしながら、事業活動全体で排出するCO2を自社で測ることは、CO2測定を事業としていない限り、まず不可能です。
そこで、一般的に活用されているのがCO2の測定と可視化が可能な各種ソフトウェア・ITツールになります。
現時点で、様々なタイプのCO2測定ツールがあり、機能やサービス、価格帯とそれぞれの状況に合ったものを選ぶことができます。
これらのITツールを総称して、「CO2見える化ソフト」と言ったり、導入することを「CO2見える化する」と言ったりします。
「CO2見える化ソフト」を使って、自社のCO2排出量の測定が簡単に実現できるのです。
CO2見える化をした際のメリット5選

CO2見える化で、企業は数々のメリットを得ることができます。
一番大きなメリットは企業の売上向上が図れることです。
1つ1つのメリットが、結果として企業に利益をもたらします。
売り上げ向上につながるメリットは、5つあります。
- コスト削減を実現
- 再エネ比率が一目でわかる
- 税制優遇、補助金が活用できる
- 商品開発・新規市場開拓のヒントが得られる
- 信頼性・将来性がアピールできる
それぞれ順番に解説していきます。
メリット1 コスト削減を実現
見える化は、CO2の発生要因を分析し、省エネ対策を講じるために大活躍するツールです。
生産過程や事業・部署別に消費電力の使用料やCO2排出量をグラフで表示、優先的に削減すべき箇所が見出せます。
年間の使用電力の例
出典:経営力強化につながる「エネルギーの見える化」‐ 経済産業局(北海道)
各室の照度を見える化した例
出典:経営力強化につながる「エネルギーの見える化」‐ 経済産業局(北海道)
上図は年間の使用電力の分布図や、各室の照度の見える化です。
「節電でもっと抑えられるのではないか」「明るすぎるのではないか」と判断材料となります。
LED照明の導入や照度の調整だけでも、約15%の省エネが可能と言われています。
コスト削減で、エネルギー生産性・付加価値を押し上げる効果が期待できるのです。
メリット2 再エネ比率が一目でわかる
省エネ以外でも、CO2を減らすために必要となるのが再エネの活用です。
見える化ツールで、再エネ比率を場所・設備機器・事業活動ごとに一目で確認することが可能です。
再エネ比率から、数台の営業車をEVに移行、特定の事業所の電力を再エネ電力プランへ変更、森林保全クレジットで足りない分を補うなど検討する機会が得られます。
また、年間・月間・週・1日ごとのデータが確認できることで、目標達成に向けてモチベーションを高めていけます。
再エネ比率のデータは外部に向けても重要なデータです。
環境イニシアティブや自社サイトの公開情報としても活用できます。
メリット3 税制優遇、補助金が活用できる
見える化のもう1つのメリットは、税制優遇や補助金が活用できる点です。
ここ数年は、2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて中小企業や小規模事業主への支援策が非常に充実しています。
見える化で導入するIT機器やシステム・ソフトを対象に、税制優遇や補助金を受けることができます。
「中小企業経営強化税」
「中小企業経営強化税」は、企業の経営力向上を支援する税制優遇制度です。
即時償却、または税額控除10%が適用されます。
3つの類型があり、見える化はC型「デジタル化設備」の導入に該当します。
ソフトウェアの購入費用70万円以上、またはその他器具備品等30万円以上からが対象です。
※あらかじめ「経営力向上計画」の認定を受けていることが申請条件となります。
中小企業経営強化税の詳細はこちら
経営力向上計画の詳細はこちら
「DX投資促進税制」
見える化の導入で、CN(カーボンニュートラル)税制の1つである「DX投資促進税制」を活用する方法もあります。
DX税制は、企業のデジタル化を支援する制度で、データ連携、クラウド化、セキュリティなど幅広くIT変革を行いたい場合に適しています。
特別償却30%、税額控除3~5%が優遇されます。
※「事業適応計画」の認定が必要です。
「見える化支援補助金」
補助金は、国が提供するものと自治体が提供するものと2つのタイプがあり、支給元が異なれば併用することができます。
国の補助金には、「IT導入補助金」「省エネ補助金」などがあり、自治体は地域ごとに様々な支援策が用意されています。
地域の広報を調べてみましょう。
税制の併用はできませんが、補助金とは併用ができる場合が多いことが魅力です。
税制と補助金にて、初期費用を最小限に抑えつつ、経営力のグレードアップを図り、売上げアップに貢献します。
メリット4 商品開発・新規市場開拓のヒントが得られる
CO2排出量は、事業活動すべての過程(Scope1、2、3)において企業責任と見なされています。
これまでは意識しなかった事業の過程においても、見える化でCO2排出の要因を探すことができます。
例えば、ありがちな例として包装や部品に使うプラスチックです。
プラスチックの素材は化石燃料です。
つまり、プラスチックの利用が自社のCO2排出量の要因だとわかることで、素材の見直しが行えます。
プラスチックに代わる天然素材は何があるか、そもそもこの部品や商品のニーズはどうなのか、新たな商品開発へのヒントが得られるでしょう。
新たな商品開発は、新たな消費者層・ターゲットを生み出します。
見える化による分析が、新規市場開拓へもつながるのです。
メリット5 信頼性・将来性がアピールできる
そして、最後にもう1つ、見える化がもたらすメリットとは、自社の再エネ比率で信頼性や将来性がアピールできることです。
Scope1、2のCO2排出量と再エネ比率の例
すでに多くの大手・中堅企業は、Scope1~3のCO2排出量と再エネ比率の見える化で、株主や取引先、消費者に公開しています。
再エネ比率の高さが企業の信頼性・将来性を表す1つの指標とされているからです。
脱炭素で世界のトップを走るAppleは、取引先も含めた再エネ比率を重要視しています。
2022年度の時点で、取引先213社が再エネへの移行を約束しているとのことです。
再エネへの移行を約束したAppleの取引先数
参照:Apple取引先213社が再エネ移行を約束 – 日経新聞
再エネ比率の高さ、あるいは向上していると証明できることが新たなビジネスチャンスや事業規模の拡大へとつながります。
資本比率の高さと相まって、再エネ比率の高さが企業価値を測る基盤となりつつあるのです。
参照:経営力強化につながる「エネルギーの見える化」‐ 経済産業局(北海道)
参照: 再生可能エネルギーの使用状況をスマホで見える化 – HITACHI
CO2見える化のデメリット3選
CO2見える化にはデメリットもいくつかありますので、ここで確認しておきましょう。
- 導入コストがかかる
- 導入だけで終わってしまう
- 企業の最終目的が見えなくなる
それぞれ順番に解説していきます。
デメリット1 導入コストがかかる
ツールの種類によって初期費用が数万円~数十万円程度、月額料金が数千円~数万円程度かかります。
「一定以上の初期費用または月額料金がかかる点」がデメリットの1つです。
デメリット2 導入だけで終わってしまう
導入するまでには何かと手間・労力がかかるものです。
晴れて導入を果たした時点で、これで終わった、と一息ついて安心してしまうケースがあります。
見える化を導入してから、本格的な削減対策が始まることを忘れないようにしましょう。
デメリット3 企業の最終目的が見えなくなる
CO2削減は、これからの新しい時代に求めらる最低限のスタンダードです。
それが経営の目的ではないことに注意しましょう。
CO2削減に集中しすぎると、本来の目的が見えなくなることが指摘されています。
CO2削減を果たしながら、利益を生み出すための長期的なロードマップが必要です。
参照: 「脱炭素社会」中小企業に必要な取り組みとは – 中小企業活力向上プロジェクトアドバンス
参照: 脱炭素経営とビジネス成長を両立するために – Free Consultant JP
CO2見える化をするために、始めるべきこと

最後に、CO2見える化の実施にあたって、準備しておくこと・始めるべきことをまとめておきました。
見える化を始めるステップ3つ
- 担当者・担当部署を決める → メインで管理できる人が必要、外部の専門家に委託する方法もある。
- 予算を決める → CO2見える化に使える予算を決めることで、ツールが探しやすくなる。
- 各種ツールを比較検討 → 情報収集・問い合わせに時間をかけて、複数のツールを比較検討
予算に合わせてどんなツールがあるのかを調べたら、機能や料金をしっかり比較検討してみることが大切です。
サポートの質も判断材料となるでしょう。
CO2見える化をさらに具体的に紹介!
https://tanso-man.com/media/co2%e8%a6%8b%e3%81%88%e3%82%8b%e5%8c%96%e3%81%a8%e3%81%af/
まとめ
CO2の可視化は、中小企業にとっても環境対策だけでなく、経営上のメリットを享受する重要な手段です。コスト削減、税制優遇や補助金の活用、新たな商品開発へのヒント提供など、具体的な利益に直結する効果が期待できます。また、信頼性の向上や将来性のアピールにも寄与し、事業の持続可能性を高めることが可能です。これからのビジネス環境において、CO2見える化は単なるコンプライアンスを超え、戦略的な投資としての価値を持つことを認識し、積極的に取り組むことが企業に求められています。
CO2削減の必要性を感じながらも、何から手をつけるべきか戸惑う事業者・経営者は多いでしょう。
そこでおすすめなのが、紙に計画や考えを書いてみることです。
紙に考えを書き出すことで、漠然とした計画が次第に整理されてきます。
CO2見える化も、紙に書いて考えを整理するのと同じです。
グラフや表で、どこでCO2が発生し、どれくらいの量なのかを知ることで、手のつけどころが見えてくるというわけです。
著者のプロフィール

- 太陽光発電・蓄電池等を専門とする住宅設備会社での勤務歴10年。再エネの専門知識からエネルギー系の株式投資と記事執筆を開始する。エネルギー専門の投資家兼ライターとして独立して7年。過去にNY、ロンドンの移住歴あり、国内・海外メディアを駆使した情報収集が強み。
最新の投稿
 CO2削減2023年10月21日【在宅VS出社】在宅ワークがカーボンニュートラルを加速させる理由とは
CO2削減2023年10月21日【在宅VS出社】在宅ワークがカーボンニュートラルを加速させる理由とは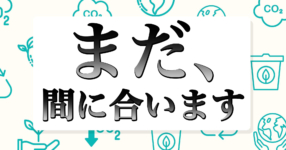 CO2削減2023年10月17日【まだ間に合う】企業がCO2見える化する一番大きなメリットとは?ソフトウェアアプリのデメリットも紹介
CO2削減2023年10月17日【まだ間に合う】企業がCO2見える化する一番大きなメリットとは?ソフトウェアアプリのデメリットも紹介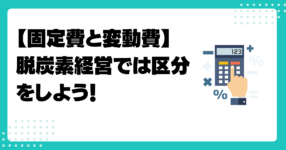 第6章2023年12月16日【固定費と変動費】脱炭素経営では区分するところから始まる!脱炭素会計の基本
第6章2023年12月16日【固定費と変動費】脱炭素経営では区分するところから始まる!脱炭素会計の基本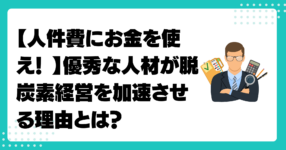 第6章2023年12月16日【人件費にお金を使え! 】優秀な人材が脱炭素経営を加速させる理由とは?GX人材の需要
第6章2023年12月16日【人件費にお金を使え! 】優秀な人材が脱炭素経営を加速させる理由とは?GX人材の需要